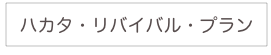種田山頭火は、明治十五年十二月三目、防府市の大地主であった竹治郎の長男として生まれた。
母の名はふさ。山頭火本名は正一といった。
十一歳のとき、父が妾を伴って遊山旅行中に、母は自宅の井戸に投身して自殺した。山頭火の悲劇的人生はここにはじまった。(のちに、三歳ちがいの弟三郎も自殺している)
十五歳で防府周陽学舎に入学、学友と共に文芸同人雑誌を発行した。のち県立山口中学に転入し、二十歳でこの中学校の第七回卒業生となったが、このころから俳句をはじめ、三田尻椋鳥句会に出席。早稲田大学予科に入学した。二十五歳神経衰弱のため退学した。
明治四十年二十六歳、父は家政に失敗して吉敷郡大道村に転居、山野酒造場を買受けて山頭火の名義で営業をした。
その翌々年、二十八歳の夏、佐波郡和田村の佐藤光之輔の長女で美人のサキノと結婚した。翌年長男健が生まれたが、このころから山頭火は文学と酒に耽り、家業を怠ってしばしば上京し、父は父で女色に溺れて失費が多く、酒倉の酒は前年につづいて二年腐るといった有様であった。
山頭火が荻原井泉水に師事し、新傾向の俳誌『層雲』に投句し初めたのは三十歳のときであった。
種田家が破産したのは大正五年彼が三十五歳のときで、父は他郷に奔り、山頭火は妻子と共に、文芸同人雑誌『白川及新市街』の縁によって、熊本市内下通りに額縁.絵葉書店「雅楽多」を営んだが、実はこれは妻女サキノの商売であった。
大正九年三十九歳、サキノと離縁。彼は上京して、区役所・図書館等に職を求めて転々し、熊本・東京間を苦悩しつつ往複し酒に溺れた。
大正十三年四十三歳、一日泥酔して熊本市公会堂前で進行中の電車の直前に立ちはだかり、電車が急停車したので事なきを得たが、そのとき、新聞記者の木庭某が彼を市内報恩寺(曹洞宗)望月義庵和尚のもとへ連れて行った。 以後、彼はこの寺に住みこみ、参禅をする。
翌十四年には、和尚を導師として出家得度し、耕畝と改名し、植木町のあたりの味取(みとり)観音の堂守となった。 しかし翌十五年には、山林独住に堪えかねて味取を去り、一鉢一笠の行乞食脚、乞食によって生きることになった。
彼が流浪の足跡は、その死にいたるまで諸国に及んでいるが、最初に福岡にきたのは昭和五年四十九歳のときで、山頭火の遺著の随一ともいうべき「行乞記」(大山澄太編『あの山越えて』)にあるように、十二月五日・二十八日に、わたしを訪れてきたのであるが わたしの家の隣家まで物乞いしてやってきたので、父は大変これを嫌い、泊めるのに困ったことであった。
また彼は、再度昭和七年の四月七日にも、わたしのところにやってきた。そのときであったか、彼の初刊本『草木塔』を春陽堂から出版する話があり、それによって定住のための資金を得るということであったので、金子三円を渡したが、すぐにそれは彼の飲代となって消え去った。
五十一歳、俳友国森樹明の好意で、小郡町矢足に其中庵ができ、安住の地を得たかに見えたが、なお心の安住の地とはならなかった。昭和十三年、其中庵が崩れたので、山口の湯田に四畳一間の家を借りて風来居と称した。
翌年、四国の松山に赴き、大山澄太の紹介により高橋一洵に頼ったが、四国遍路ののちには、道後湯町の木賃宿に滞在した。そこで一洵の世話によって、松山市御幸町御幸寺門外の一草庵に止住することを得た。一草庵の庵名は澄太の名づくるところ、現在の松山護国神杜のところである。
昭和十五年五十九歳。五月、句集『草木塔』が出版され、広島から北九州にかけて旅に出たりしたが、十月十日、午後脳溢血で倒れた。まったくの「ころり往生」で、人びとがその夕刻に催される「柿の会」に来庵して、手当をしたが、翌十一日の午前四時(推定)に絶命した。
以上は、「草木塔年譜」からの摘録に、少々の私縁をからませての記述であるが、とにかく最近の山頭火ブームは大山澄太らによって山頭火を俳聖化して宣伝したところによるものが多いと思う。澄太は戦時中に『軍神杉本中佐』を書いて、大いに稼いだ男である。山頭火を偶像化することによって、利益をうけるのは澄太である。
わたしは、山頭火に接して澄太のような扱いはできない。山頭火は俳人として漂泊をしたのではなく、放浪をしつつ俳句に生きたもので、酒は飲む、僧形であっても女は買う。彼ごとき無修業で僧侶としての資格が与えられるということ自体がおかしいと思う。
山頭火の文学は、松尾芭蕉の文学とはまるで違った境涯のものである。芭蕉は旅に出てもかならず同行の弟子を伴い、座の文学としての俳諧の本道をはずれることはなかった。
山頭火のようにどろどろとした人間生活は、ついに孤であり、個の文学としての彼自身のみの俳境でしかなかった。彼は、行乞の旅をつづけながらも、つねに心底にうごめいていたのは、別れた妻へ、安住できそうな家庭への執着であった。それができなかったところに彼の悲劇があったので、真の世捨人では実はけっしてなかったと思う。
わたしは、そのような特殊の境涯というか境遇のなかで苦吟していった彼の俳句に、心をうたれるもののあることを認め、かつ相当の評価を与えてよいと思うのである。
ここに若干の句を連らねて、「困った困った」といいながら、多くの人びとが愛してくれた、その種田山頭火の孤独に徹した俳風を偲んでもらうことしよう。
種田山頭火句抄 (三宅酒壺洞 撰)
松は皆枝垂れて南無観世音
分け入っても分け入っても青い山
生死のなかの雪ふりしきる
へうへうとして水を味ふ
笠にとんぼをとまらせてあるく
ほろほろ酔うて木の葉ふる
しぐるるや死なないでゐる
しみじみ食べる飯ばかりの飯である
どうしやうもないわたしが歩いてゐる
まったく雲がない笠をぬぎ
雨だれの音も年とった
見すぼらしい影とおもふに木の葉ふる
あるひは乞ふことをやめ山を観てゐる
笠も漏り出したか
うしろすがたのしぐれてゆくか(自嘲)
ふるさとは遠くして木の芽
いただいて足りて一人の箸をおく
ぬいてもぬいても草の執着をぬく
こころすなほに御飯がふいた
家をもたない秋がふかうなるばかり
曼珠沙華咲いてここがわたしの寝るところ
あるけば草の実すわれば草の実
柳ちるいそいであてもない旅へ
誰にも逢はない山のてふてふ
何を求める風の中ゆく
わかれて遠い人を佃煮を煮る
やっぱり一人はさみしい枯草
うまれた家はあとかたもないほうたる
死ねない手がふる鈴をふる
水音けふもひとり旅行く
一握の米をいただいてまいにちの旅
おちついて死ねさうな草萌ゆる
其中雪ふる一人として火を焚く
雪へ雪ふるしづけさにをる
酔うてこほろぎと寝ていたよ
雨ふるふるさとはだしであるく
けふのみちのたんぽゝいた
( 昭和五〇・六・七 宗教文化懇話会における卓話の要旨 )